あらゆる角度から生き物の理解を深めたい
プロフィール
牧田夏実ニコル(マキタ ナツミ ニコル)さん。応用生物学部環境生物科学科3年。岐阜県立可児高校出身。日本人の父とチリ人の母を持ち、日本語・英語・スペイン語のトリリンガルを目指す。生き物を観察したり、自然に触れることが好きで、大学では応用生物学部に所属。
課外活動では、里山サークルに参加して地域課題の解決に取り組む他、海外でのホームステイや友人との海外旅行などを通じて、グローバルな関心も高めている。好きな食べ物は母が作るスペアリブで、ハーブと塩コショウでシンプルに味付けした肉からは噛むと肉汁が溢れ、絶品だという。
中部大学を選んだ理由

「幼少期から高校生までは特に人と関わることが苦手で一人でいることが多かったです。一方で、自然を身近に感じる環境で暮らしていたこともあり、5歳年上の兄とよく外に出て生き物を観察していました。また乗馬クラブで馬と触れ合っているなど、生き物は以前から好きでした。
自分の進路を考えた時に、将来は大好きな生き物に関わる仕事をしたいと考え、自宅からも通学可能な生物系の学部がある中部大学に入学しました。また、生物を学ぶ際には、机上だけでなく、野外にも積極的に出たいと考えたので、フィールドワークが多い環境生物科学科を選びました」
学科での勉強内容
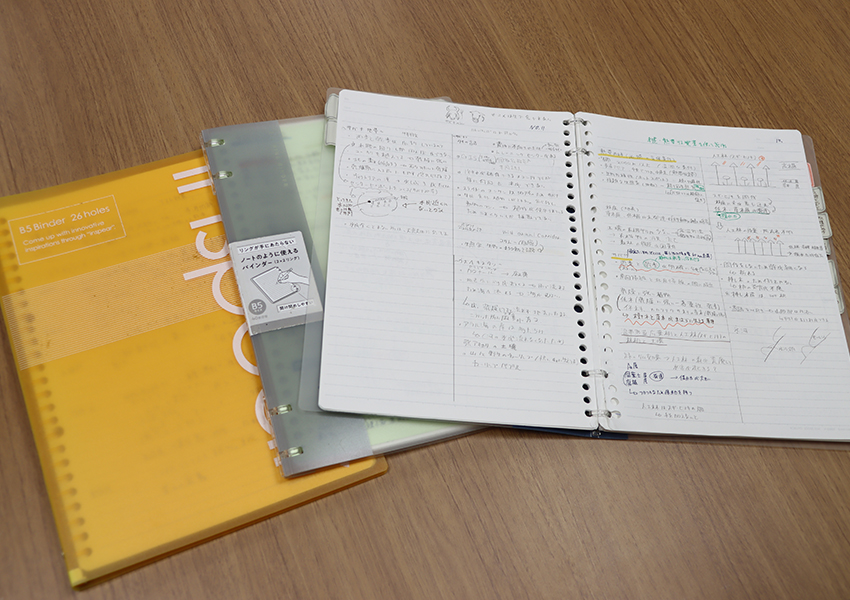
「環境生物科学科では、生物に関連する基礎的な知識に加えて、環境問題や自然保護、生物多様性といった応用的な知識まで幅広く学んでいます。各講義を受けることで、本当に自分にとって興味のあるものや熱中できるものを見つけることができると感じています。
中でも1年生の秋に受講した大場裕一教授(環境生物科学科)の『生物多様性概論』は、特に印象に残っている授業の一つです。この授業では生物の分類について自分で系統樹(生物の進化の過程を枝分かれさせながら表した図)を書いて学びました。現在確認されている生物を、形態や生態などの観点で、原子生物から見ていくと、それまで知らなかった不思議な生物がいることや、近い分類だと思っていた生物同士が実は進化系統的には離れていることも知ることができ、とても楽しんで受講していました」
里山サークルでは立ち上げメンバーの一人として活躍

「1年生の秋学期に、2023年度入学の環境生物科学科の学生が主体となって里山サークルを立ち上げました。(里山の利活用を学ぶ里山サークルが発足しました)
このサークルは、恵那キャンパスの森林やその環境を利用することで、もっと学生の集う場所として盛り上げようと始めたものです。間伐によって森林に残された林地残材の活用法を見つけることも活動のねらいの一つです。
サークル内には哺乳類や野鳥の調査を行う係や間伐の係があり、私は野鳥の調査と間伐を担当しています。野鳥の調査では、恵那キャンパス内でバードウォッチングをします。私はまだまだ未熟なのですが、手慣れている部員は鳥の姿を見ただけでなく、鳴き声や飛び方から野鳥の種類を判別できるほどです。私も早くその域に達することができるように日々勉強しています。
間伐では、実際にチェンソーを使って、木を切り倒し、切った木の利活用について検討しています。研究段階ですが、木材を食材として活用した飲み物や食べ物を作ってメンバーで食べてみたいと考えています。
また今年は初めて大学祭にも出店しますが、将来的には、これらの活動の中で開発した商品も提供できればと考えています」
1カ月間アイルランドでの生活を経験

「日本を離れての生活をしてみたいとずっと考えていたので、2年生の夏にアイルランドで1カ月間のホームステイをしました。アイルランドでの生活は至福のひと時で、ホームステイ先の家族や友人だけでなく、街ですれ違う人々も皆温かく、優しい人ばかりでした。通りすがりの人が必ずと言っていいほど、あいさつをしてくれて、仲間意識の強い文化が根付いていると感心しました。バスに乗った際には、降車する人がみな運転手に向かって『Thank you!』と感謝の気持ちを述べていて、とても素敵でした。
またアイルランドの首都ダブリンにあるテンプルバーというエリアにはアイリッシュパブが密集しています。そこに何軒か行ったことも印象に残っています。みんなでお酒を飲みながらカントリーミュージックやフォークソングを聴くことがとても楽しかったです。
滞在中苦労したことはあるかと聞かれると、『全くない』と即答できてしまうほど、充実した生活でした。まだ決まったわけではありませんが、今後自分の研究テーマを学ぶため、どこかの国で留学できたらと考えています」
生き物の標本づくりをするボランティアにも参加


「学外での活動の一つとして、博物館での標本づくりのボランティアも行っています。自分の趣味として、生き物の標本づくりを行ってみたいと思ったことがきっかけでしたが、自分で一から学ぶよりも、誰かに教えてもらった方がより身に付くと思いこの活動への参加を決めました。
作る標本は、哺乳類や昆虫など人によってさまざまですが、私は鳥の標本づくりを主に行っています。標本に使われる素材は、主に事故で死亡した個体が使用されます。中には状態が悪い個体もありますが、傷を縫うなどして、きれいに仕立てます。標本を作る際には腹を切り開いて、中身をすべて取り出すのですが、臓器などが図鑑通りの配置になっている様子をみると、生き物の体のつくりはこのようになっているのだと感動します。
この標本づくりは、自分が作った資料が博物館に展示される達成感を得られると同時に、生き物を知るという意味でもとても勉強になる活動だと思います」
広い視野を持って、博物館の学芸員を目指す

「今は、学芸員課程を履修し、資格取得を目指して勉強しています。学芸員になることは狭き門だと授業で何度も聞きましたが、今は難しいことであっても、諦めずに自分が好きなことに向かって努力したいと思っています。また、自分自身の成長のために、大学院へ進学し、自分の研究にとことん向き合っていきたいです。さらに、他の学問や環境問題などの社会問題も学ぶことで、広く視野を持って活動できる人間になることが目標です。好きな自分になれるように、やりたいことに挑戦することをこれからも続けていきたいと思っています」


