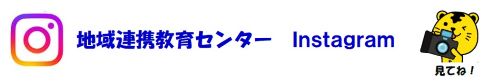学ぶ意欲を持つ人のニーズに応えるカリキュラム。

CAACでは、2021年度より生活・科学の科目を開講しています。趣味や暮らしの延長として楽しみながら、専門的な知識を得ることで、さらなる活躍の可能性を広げられることでしょう。また、健康・福祉コースでの学びは、ご自身の健康に役立つことはもちろん、ご家族、ご友人、ひいては地域の健やかな未来へつなげられます。学びたいことが明確な方はもちろん、「夢中になれる何かを探したい」という方にもCAACはぴったりです。1年次には共通科目としてコンピュータ入門、ポルトガル語入門など、幅広い講義を用意しています。CAACで学ぶ2年間は、言わば第二のモラトリアム。これからの人生をあなたらしく、軽やかに生きていくための学びが、ここにはあります。

對馬 明教授(生命健康科学部 理学療法学科)
健康・福祉コース長
担当科目:「健康増進実習」「身体の構造と機能」「臨床医学(施設見学)」
地域に貢献し、次世代のために学び、生きていく力を。

私たちが若いころに学んだ一国主義のもとでの“国際社会”とグローバル化が進んだ現在の“国際社会”とでは、その在り方は大きく変化しています。例えば地球温暖化による巨大災害などがその事例です。自分の「常識」が、実はグローバル化時代には通用しなくなっていることも。そこで大切になってくるのが、新しいこと・知らないことを、共に学び合える場と仲間との出会いです。国際・地域・文化コースでは、グローバル化時代を生き抜く力を身に着けたい、地域社会に貢献したい、次世代のために学び続けたいと願う前向きな方を歓迎します!

羽後 静子教授(国際関係学部 国際学科)
国際・地域・文化コース長
担当科目:「国際社会を見つめて」「持続可能な地域社会」「国際社会と文化」
「地球環境と災害」
新たな場所で挑戦を始める受講生の背中を後押ししたい。

人が生きていく以上、必ず多くの人と関わり、協力していく必要があります。「組織の中の人間行動論」では、会社組織をメインに扱いながら、地域コミュニティやボランティア組織などでの活動にも役立つ授業を目指しています。経験豊富な受講生のみなさんに組織の理論を伝えることで、「あのときのあの経験は、こういうことだったのか」と新たな発見をしていただけるでしょう。また、これから地域の自治体やコミュニティで活動される場合、周りと新しく関係をつくっていかなければなりません。そのときに起こりがちなトラブルやその解決方法、周りの人を巻き込む方法などを伝えたいと考えています。理論を学んで現実をみると、絶対に新しい景色が見えてきます。新たな挑戦をしたいと考える、受講生の背中を押すような授業にしたいですね。

寺澤 朝子教授(経営情報学部 経営総合学科)
共通科目担当
担当科目:「組織の中の人間行動論」
誰でも、いつまでも健康で学び続けて欲しい。

いつまでも自立し、健康的に生活できること。いつかは誰もが関わっていくテーマです。授業では加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して健康を保持増進し、自ら要介護状態となることを予防し、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションや適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その人の持っている能力の維持向上に努められるようにしていきます。講義や実習を通じて、理学療法学科の学生と現役の理学療法士、CAACの受講生が互いに手を取り、学び、教え合うことで、さまざまな立場からの気づきや発見を得られることでしょう。そして健康なうちは要介護者に寄り添える「あてになる人」であり続けていただきたいと思います。
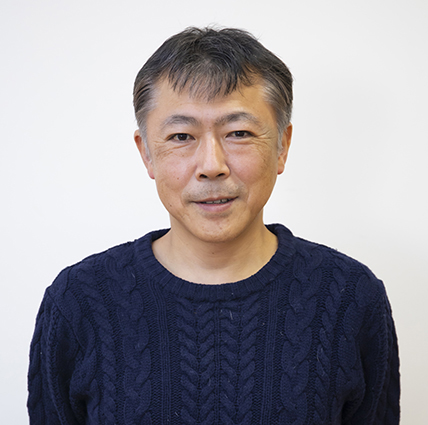
宮本 靖義准教授(生命健康科学部 理学療法学科)
健康・福祉コース
担当科目:「リハビリテーションとピラティス」「高齢者福祉と介護保険法」
認知機能と身体活動・運動の関係を学び、
ご自身と周りの方々の健康寿命を伸ばす。

私の科目では認知機能異常をはじめとした生活習慣病と身体活動・運動の関係性を学びながら、健康増進を目指して運動実習を行います。本コースの受講生はもともと健康意識が高い方が多いですが、年齢や背景が異なるため、一人ひとりの運動負荷を考慮することはもちろん、授業前に血圧測定や体調のチェックを行うなど、安全に楽しく実践していただける環境づくりを心がけています。認知機能テストや体力・運動能力測定などを実施し、定期的に自身の状態をフィードバックしていますが、「実習を通じて健康になった」という声もいただき非常にうれしく思っています。私の所属する学科の学生が運動指導スタッフとして運動プログラムを提供・実践しており、世代を越えてお互いに健康増進を学び合います。身体活動・運動は身体だけではなく脳にもポジティブな影響を及ぼします。その効果を一緒に実感してみませんか。
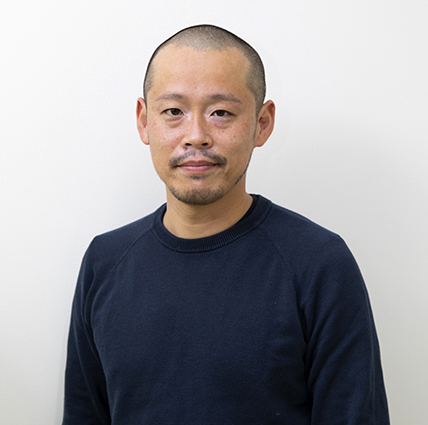
水上 健一准教授(生命健康科学部 スポーツ保健医療学科)
健康・福祉コース
担当科目:「健康増進実習」
好奇心を原動力に、楽しみながら学びを深める。

講義では漢字発祥の地、中国をはじめ、韓国、ベトナム、そして日本の漢字文化圏をターゲットにして、言語における共通点、相違点などを説明しています。外国語を身近に感じられるよう、堅苦しい勉強ではなく実践的な学びになるような授業を心がけています。中国語の歌を歌ったり、それぞれの言語で自分の名前を書いてみたり、中華料理の調味料の単語を覚えたり、身近なところから外国語に触れ、慣れていってほしいと思います。さらに海外旅行に行ったときに、「メニューをください」など現地の言葉で伝えられると良いなと思います。日本でも本格的な中華料理屋で中国語を使って注文してみるのも面白いですよ。好奇心を満たすことは、人生において大切なことだと思います。好奇心旺盛なCAACの皆さんに刺激を受けながら、全力投球で授業に取り組んでいます。

伊藤 正晃講師(国際関係学部 国際学科)
国際・地域・文化コース
担当科目「東アジアの言語と文化」
お問い合わせ先
中部大学 地域連携教育センター CAAC事務局
電話: 0568-51-1763 FAX: 0568-51-1172 Eメール: chubu-chiiki@fsc.chubu.ac.jp
取扱時間: 月曜日~金曜日 9時~17時