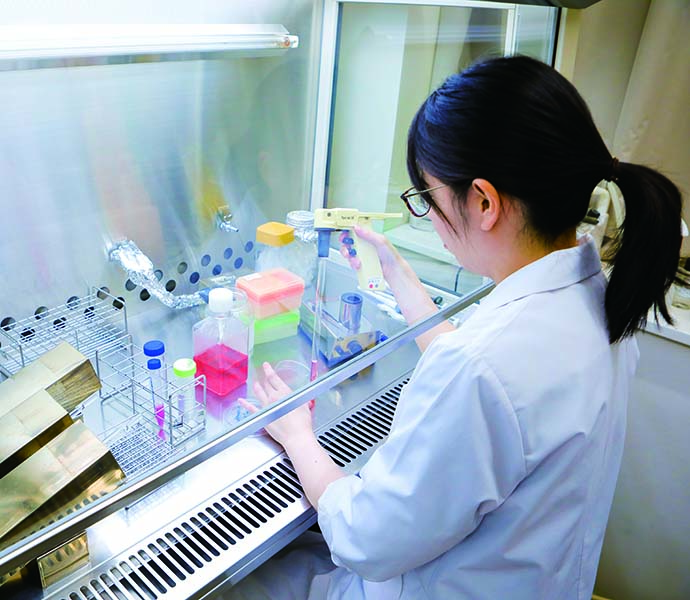生物機能開発研究所とは
生物機能開発研究所は、応用生物学部・応用生物学研究科における研究活動の牽引役として学部・研究科における研究力の維持・向上により応用生物学部・応用生物学研究科のアクティビティとプレゼンスを高めることを目的としています。
有望な研究プロジェクトや意欲的な若手研究者の育成、研究環境の整備、寄附研究部門の支援、ライフサインエンスフォーラムを含む講演会やセミナー等の開催などの研究力の向上に向けた取り組みを実施するとともに、研究所ならびに応用生物学部・応用生物学研究科のプレゼンスを高めるために研究所の活動や実施プロジェクト、関連研究成果を外部に発信することにも取り組み、その一環として生物機能開発研究所紀要を発行しています。
また、研究環境の整備に向けて科研費を含む外部研究資金獲得の支援、大学院生の研究活動や研究発表の支援も行っています。
プロジェクトメンバー
プロジェクト(2025年度)
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
| Non-conventional酵母の糖脂質生産性の評価とゲノム解析 | 渡部貴志准教授(食品栄養科学科) |
| フェアリー化合物代謝関連酵素の機能開発 | 伏見圭司准教授(応用生物化学科) |
| 食品旨味成分「コハク酸」の新たな役割の解明: ベージュ脂肪細胞化による抗肥満効果からのアプローチ | 津田孝範教授(食品栄養科学科) |
| シアノバクテリアにおけるストレス応答性リパーゼの同定 | 愛知真木子准教授(応用生物化学科) |
| 里山保全のための、恵那キャンパスにおけるムササビの生態調査 | 上野薫准教授(代表、環境生物科学科) 土田さやか准教授(環境生物科学科) |
| 光触媒を用いたアオコ防除手法の検討 | 程木義邦准教授(環境生物科学科) |
研究補佐員(2025年度)
| 研究者 | 研究課題 | |
|---|---|---|
| オウ ギョウソ | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | ウチワサボテンのアスコルビン酸蓄積の低温環境ストレス応答性に関する研究 |
| 安藤 捺稀 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 糸状菌Aspergillus terreusにおける有機酸生産制御に関する研究 |
| 石上 まりの | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 食事の違いが大学サッカー選手のパフォーマンスに与える影響について |
| 鵜飼 実桜 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 大豆発酵食品における適合溶質エクトインの分析 |
| 大橋 一摩 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 柑橘類ポリメトキシフラボノイド(PMFs)及びその誘導化合物によるHDL産生促進機構の解明 |
| 川本 里奈 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 葉の発生・分化におけるrRNA遺伝子座の核内局在性に対するAS2の役割の解明 |
| 菊地 天音 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | ウチワサボテン(Nopalea cochenillifera)継続摂取がマウスの免疫機能および腸内細菌叢に及ぼす影響 |
| 小泉 ありさ | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | キシラン資化性Clostridium perfringensの構築 |
| 高山 愛莉 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | ウチワサボテン添加がアイスクリームの物性に及ぼす影響 |
| 谷 葵衣 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | 糸状菌Aspergillus terreusにおけるイタコン酸生産制御に関する研究 |
| 陳 奕先 | 応用生物学研究科 応用生物学専攻 2年 | レポーター遺伝子を用いた遺伝学的手法により同定したVTC2発現制御候補遺伝子の過剰発現がアスコルビン酸生合成に及ぼす影響 |